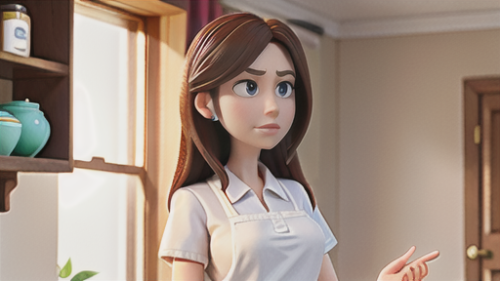介護保険
介護保険 要介護状態とは何か?
人が年を重ねたり、病気やけがをしたりすることで、日常生活を送るのに支えが必要になることがあります。この状態が6か月以上続くと、要介護状態と認められる場合があります。
要介護状態とは、簡単に言うと、一人で普段の生活を送るのが難しくなった状態のことです。例えば、ご飯を食べたり、お風呂に入ったり、トイレに行ったりといった基本的な動作でさえ、誰かの手伝いが必要になります。
体の機能が衰えたり、心の病気を患ったりすることで、このような状態になることがあります。また、けがが原因となる場合もあります。
要介護状態には段階があり、要介護1から要介護5までの5段階に分かれています。状態が軽い場合は要介護1、重い場合は要介護5と判断され、どの段階になるかによって受けられる介護サービスの種類や量が変わってきます。
要介護と認められると、介護保険のサービスを受けられます。自宅で介護を受けたり、介護施設に入ったりと、さまざまなサービスから自分に合ったものを選ぶことができます。
サービスを受けるには、住んでいる市区町村に申請し、審査を受ける必要があります。この審査によって要介護の段階が決まります。
要介護の認定を受けることは、介護が必要な状態であることを客観的に証明するものであり、自分に合った支えを受けるためにとても重要です。家族など介護をする人にとっても、介護の負担を軽くするための助けとなるため、なくてはならないものです。
要介護状態は人それぞれです。状態や程度も違いますので、それぞれに合った丁寧な介護が必要です。適切な介護を受けることで、生活の質を保ち、できる限り自分の力で生活していくことができるようになります。