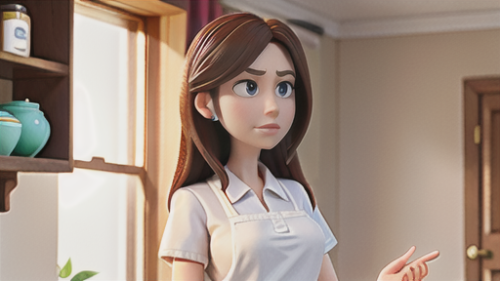訪問による介護
訪問による介護 ホームヘルプサービスで安心の暮らし
ホームヘルプサービスとは、自宅で安心して暮らし続けたい高齢の方や障がいのある方、病気で日常生活に不自由がある方を支えるための在宅サービスです。専門の資格を持ったホームヘルパーが自宅を訪れ、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかな援助を提供します。
大きく分けて、身体介護と生活援助の二つのサービスがあります。身体介護は、食事や入浴、トイレの介助、更衣、体位変換など、直接体に触れて行う介助です。加齢や障がいによってこれらの動作が難しくなった場合に、ホームヘルパーがサポートすることで、安全かつ快適に日常生活を送れるようお手伝いします。たとえば、入浴介助では、洗髪や洗体だけでなく、浴槽への出入りや着替えの補助も行います。
生活援助は、調理や洗濯、掃除、買い物といった家事全般の支援です。利用者の状態に合わせて、必要な家事だけを依頼することも可能です。たとえば、調理が困難な方には、栄養バランスを考えた食事作りを支援します。また、掃除が負担になっている方には、部屋の掃除や片付けを行います。
ホームヘルプサービスを利用するには、ケアマネージャーに相談し、ケアプランを作成してもらう必要があります。ケアプランとは、利用者の心身の状態や生活環境、希望などを踏まえて作成される、サービス利用計画書のことです。このケアプランに基づいて、必要なサービスの種類や時間、回数などが決定されます。ホームヘルプサービスは、他の介護サービスとの連携もスムーズに行えるため、総合的な在宅支援が可能になります。住み慣れた我が家で、安心して自分らしい生活を送れるよう、ホームヘルプサービスは様々な面から利用者を支えます。